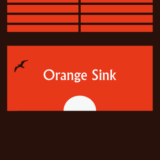読書:ヒッタイトに魅せられて / 大村幸弘、篠原千絵
学生のころ、日本の女子高生が紀元前14世紀のヒッタイト帝国にタイムスリップしてなんやかんや成り上がる少女漫画『天は赤い河のほとり』を読んでいたことがあったので、この本を見たときは「ヒッタイトか〜懐かしいな〜」くらいの気持ちで手に取ったのだが、その『天は赤い河のほとり』の著者・篠原千絵先生と、実際にヒッタイトの周りで発掘を行なっている日本の考古学者・大村幸弘先生の対談本であることが発覚し、びっくりして読み進めてしまった。な、なぜ今になって?漫画が無事完結してから10年以上は経っとらんか?とは思いはするものの、対談本の合間に挟まれる篠原先生の絵柄に懐かしさでいっぱいになってしまうなどした。天は赤い河のほとり〜!私に、悪女とラムセス二世と予防接種の大切さを教えてくれた漫画!
本を読み進めて、すぐにビックリしたことなんだけど、ヒッタイトって今のトルコの位置にあたるんだ。……エッ?ということは、2023年2月に起きたトルコ・シリアの大地震でトルコの遺跡も相当被害に遭っているのでは?ということに気づいてしまい、大変ハラハラしながら読み進めることとなった。
以下メモ。
・まず、日本がトルコの遺跡の発掘権を買ってデカめの施設を建てていた(アナトリア考古学研究所)ということ自体が初耳だったので、海外の遺跡の発掘調査するって本当に大変なんだなあ……という当たり前の感想が浮かぶ。トルコ大学の重鎮の先生方や、日本の皇族の殿下のお力がなければ、トルコからの信頼を得たりすることも、発掘費用を集めたりすることもできず、遺跡の発掘権を得ることができない。確かになあ。海外の考古学者が単身で乗り込んで遺跡発掘なんていうことはできないよなあ。他国の遺跡を発掘しようとすると、政治的な交渉と現地の理解が欠かせないらしい。また、遺跡発掘を進めるにあたって現地住民を大量に雇う必要があるらしく、雇用問題も起きるとのこと。
・対談者である大村幸弘先生は、考古学者としての己の目的のみでこの遺跡発掘を行おうとはせず、長期的に次世代の若手を育てるためであったり、動物考古学や地学、保存修復、形質人類学等といった他分野の学者との交流を図るためであったり、また現地の住民の雇用を生んだり、現地の子供達に直に歴史の欠片を触らせたりと相互理解に努めつつ、四苦八苦しながらさまざまなアプローチを試みておられる様子。エッ素晴らしいな…。
・漫画『天は赤い河のほとり』の男主人公のモチーフになった人物、ヒッタイトの王・ムルシリ2世のペスト祈願文書の解読が、漫画の連載終了にできて、内容が「神々にペストをなんとかしてくれという祈願、悪いのは父であって私たちではない、なぜ私がその罪を受けねばならないのか」みたいな切々と神に哀願したものだったので、著者が「これを連載中に知っていたら少し情けない性格にしてたかもしれない」的なコメントをしていて、笑ってしまった。
・でも、隣国のエジプトは「俺ことファラオが神!ファラオは絶対!」というような文化なのに、この文化的な違い(ヒッタイトでは、王であるこの身は人であり、神々に希う下々のものであるという自覚が王にある)は確かに面白い。考古学者の先生は、「エジプトの遺跡は黄金のマスクとか金銀財宝とか出て、それを元にエジプト展とかで集客できるのに、ヒッタイトは粘土板や土器ばっかり出て地味です」みたいなのも涙してしまった。確かにな……。製鉄や粘土板の話は聞くが、ヒッタイトやトルコから派手なものが出たって印象はない。
・意外だったのは、トルコといえば黒海にも地中海にも面していてユーフラテス川もあるのに、水資源とは関係のないバチバチの山岳地帯にヒッタイトの首都があったらしいこと。なんでよ?という疑問に明確な答えはないのだが、山岳地帯は強い風が吹く→製鉄に必要な1000度を超える高温の火を用意するのに風を用いた?みたいな仮説が出てきて、ちょっと興味深かった。
・あと、ヒッタイトの首都、冬はマイナス15度になるくらい寒いらしい。エ!?エジプトの近くってんで、てっきり年中温暖な気候だと思っていたが!?
・欧米の学者たちはやっぱり強い。歴史もある。余裕もある。世界中の小麦のサンプルとかを持っているので参照力がある。強い。
・ヒッタイト=製鉄技術でブレイクスルーを起こした連中ってイメージだったが、鉄はそんなに遺跡から出てきてないらしい。鍛治所も見つかってないとのこと。そんなバカな。じゃあなんでヒッタイト=鉄!ってイメージがあるんだよ、と思ったら、一応鉄にまつわる書簡(粘土板)みたいなのが遺跡から出てきて、「鉄の武器は今製作中なんで追々送りますよ」と記されていたことが確認できてたからっぽい。書簡(粘土板)は強い。
・カムメンフーバー先生とおっしゃる方が、来日されて、奈良のお寺の仏像のそばにあるサンスクリット文字を見て「これはインド・ヨーロッパ語族、つまりヒッタイト語とも結びつきがある」とコメントしたくだりは胸を打たれた。世界は繋がっとる…!
・最終的にヒッタイトは、海の民に滅ぼされた、天災があった、病疫や飢餓があったなど諸説あるもののこれといった原因が特定できないまま滅びたわけだが、漫画を描かれた篠原千絵先生は、その滅びた後である現在のトルコの遺跡の荒びを見て、「最終回のシーンはこの風景だ」と連載前から決めていたらしい。篠原千絵先生、自分の漫画のことはさておいて、ずっとヒッタイトに関する質問を考古学者の先生に投げ続けており、本当にヒッタイトに魅せられていたんだなあと思えた。今はオスマン帝国の漫画を連載中であるとのこと。機会があったら読んでみたい。
以上。昔に愛読していた漫画を思い出してとても懐かしかったし、考古学・遺跡発掘の知見を得ることもでき、めっちゃ面白い本でした。